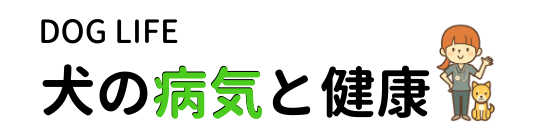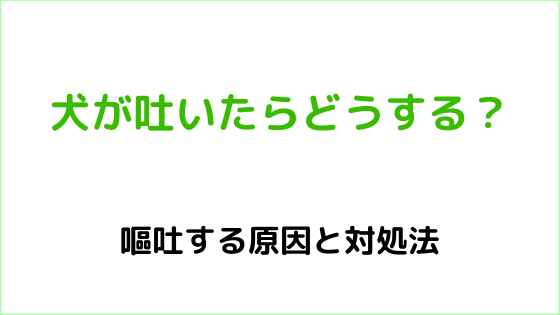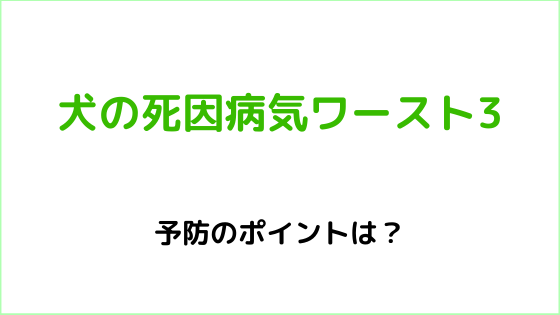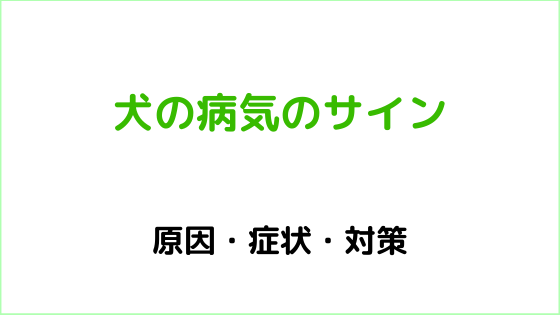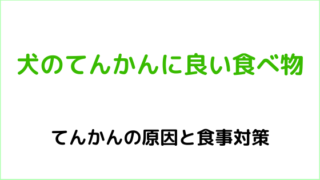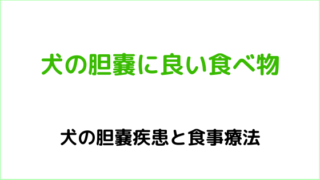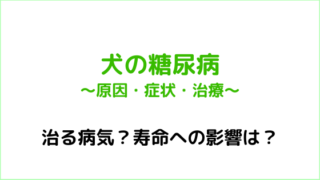愛犬が急に吐いてしまったら、どうしたらいいか焦ってしまいますよね。
「犬はよく吐く動物」と言われていますが、いざ愛犬が吐いてしまうと心配です。
★犬の嘔吐で次のような症状があればすぐに病院に行ってください。
・苦しそう、グッタリしている、元気がない
・発熱している
・嘔吐と下痢がある
・けいれん、よだれ、呼吸がおかしい
・繰り返し吐く
・2日以上吐く状態が続く
・吐いた物が茶色い、血が混じっている
(古くなった血液の場合、赤色よりも茶色・黒っぽいです)
・吐いた物から便臭がする
・吐いた物に異物が混じっている
この時、犬が吐いた物は診断するとき重要なヒントになります。
吐いたものをラップで包むかビニール袋に入れて持参し、吐いた時の状況も説明できるように整理しておきましょう。
一方で明らかに原因がはっきりしていて(車酔いなど)、犬も元気ならすぐには病院に行かず、様子観察でいい場合もあります。
今回は犬吐く理由と原因、吐いた時の対処法、吐いた後の食事、慢性的に吐く犬の対策を紹介していきます。
●すぐに見たい項目があれば下の目次よりお選び頂けます
目次
「犬が吐く」には3種類ある

嘔吐(おうと)
ある程度消化されたものを吐き、吐いたものはあまり食べようとしないのは嘔吐です。
食べたものが消化されているので原因は胃や腸などの消化器官のトラブル、腎臓や肝臓の病気などが考えられます。
吐き気を感じ、落ち着きがなくなる・口の周りを頻繁に舐める・よだれを垂らすなどの前兆が見られることがあります。
頭を下げ腹部を大きく動かしゲッゲッと音を立て、そのあとに吐き出すことが多いです。
吐出(としゅつ)
吐いたものは消化されていないのが特徴です。
力強く飛ばすように吐き、吐いたものをもう一度食べることもあります。
吐いたものが消化されていないことから、原因は喉や食道にあるといわれています。
通常は吐く前に悪心や吐き気などの前兆は見られません。
嚥下困難(えんげこんなん)
食べ物をうまく飲み込めずに吐き出してしまうことをいいます。
この場合、吐いたものは消化されていません。
原因は飲み込む部分である口腔・喉・食道にあるといわれています。
嚥下障害で吐く犬は、咳き込むような様子が見られるようです。
遺伝的な場合、何らかの疾患がある場合、筋力の衰えから起こるものもあります。
嚥下障害は人間と同様に誤嚥性肺炎の原因になりますので注意が必要です。
犬が吐いて、こんな症状もあるならすぐに病院へ
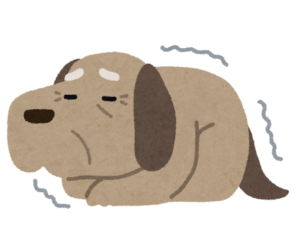
★苦しそう、グッタリしている、元気がない
★発熱している
★下痢がある
★けいれん、よだれ、呼吸がおかしい
★繰り返し吐く
★3日以上吐く状態が続く
★吐いた物や便に異物や血の混入が見られる
(体内で出血し、古くなった血液の場合、赤色よりも茶色・黒っぽいです)
★吐いた物から便臭がする
上記の症状が見られたらすぐに病院へ行ってください。
犬の嘔吐を引き起こす主な病気
・消化器疾患…
胃腸炎、膵炎、腸閉そく、胃捻転 など
・内臓疾患、全身疾患…
腎臓病、肝臓病、糖尿病、腫瘍、熱中症 など
・感染症…
ウイルス、細菌、寄生虫 など
・中毒…
チョコレート中毒、農薬、除草剤 など
病院へ連れていく時に注意すること
獣医師には、
・いつ、どんな状況で吐いたのか
・どのくらい続いているのか
・何かを食べて(飲んで)吐いたのか
(チョコレート、玉ねぎ、タバコ、除草剤、キシリトールガムなどは中毒をおこします)
・吐いた物の形、色、におい
などを詳しく伝えられるようにしましょう。
可能なら、吐いたものをラップで包むかビニール袋に入れて持参しましょう。
その時は感染症予防のため、密閉できる容器か袋に入れてください。
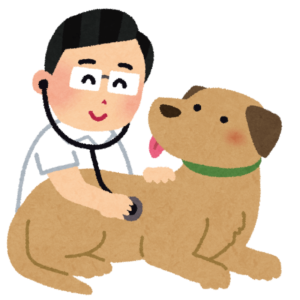
人間への感染予防もわすれずに
嘔吐物や下痢の後片付けをする時は手袋をしましょう。
水ぶきや洗剤だけでは細菌やウイルスを防ぐことはできませんし、一部のウイルスはアルコール消毒では不十分です。
強力な除菌・消臭効果があって、愛犬の目や口に入っても大丈夫な除菌スプレーを使ってきれいに掃除してください。
しばらく様子を見ても大丈夫なもの(一過性のもの)
・1回か2回吐いて、その後は吐かない
・他に症状がない
・吐いた後いつも通り元気
・明らかな原因がある※
このように吐く以外に症状がなく、特に変わった様子がない時にはしばらく様子を観察してもいい場合があります。
※明らかな原因としては以下のものがあります。
◆ 大食い、早食い
食べ過ぎて消化できずに吐く、早食いでよく噛まずに飲み込んで吐くパターンです。
食べっぷりがいいと嬉しくなりますが、消化できなければ体に良くありません。
対処方法は、ご飯を小分けに出す、ドッグフードは小さな粒にするなどです。
ただし、小粒にすると余計丸のみする場合があるので、あえて大きめの粒に変えてみるとよく噛んでくれることがあります。
◆ 水の飲みすぎ
ドッグフードを食べた後に水をたくさん飲むと、胃の中で膨張して吐いてしまうことがあります。
乾燥したジャーキーなどは水分でかなり膨らみますので気をつけましょう。
冷たすぎる水も胃を刺激するので注意が必要です。
◆ 食後の運動、散歩
食後に激しい運動や散歩をすると、消化不良や胃捻転の原因になります。
散歩の後しばらく休んでからご飯という流れが安全です。
食後に興奮して遊びだすワンちゃんもいますが、なるべく静かにして消化できるようにしましょう。
◆ 車酔い
車に乗っていて、舌をペロペロ、息がハアハア、口をクチュクチュ、落ち着かなくなったら酔っています。
こうなる前に窓を開けて新鮮な空気を入れたり、まめに休憩をとってあげてください。
◆ 注射、お薬
ワクチン接種、お薬には作用と副作用があります。副作用で吐くこともありますので、注射したり、お薬をもらった時にはよく説明を聞きましょう。
※嘔吐したタイミングによってはもう一度お薬を飲ませる必要がありますので、病院に連絡して確かめてください。
◆ 空腹時に吐く
朝方や空腹が長く続いた時に、黄色(胆汁)や白い泡状の液体(胃液)を吐くことがあります。
消化器官が未発達な子犬に多くみられます。
犬は空腹が続くと胃液や胆汁が逆流するので、餌をあげるタイミングを調節してください。
◆ アレルギー
長い間食べ続けていたドッグフードで吐くようになったり、何か特定のフードを食べたら吐くという場合はアレルギーかもしれません。
かゆがる、発疹、目の充血、目やに、鼻水・くしゃみ、脱毛など見られたら病院で検査してください。
◆ 草を食べて吐く
犬が草を食べて吐くのは有名ですよね。
「胃の調子を整えている」と言われることもありますが、実際はなぜそのような行動をするのかわかっていません。
農薬や除草剤の危険性があるのでなるべく食べさせないようにしましょう。
◆ 毛玉を吐く
胃の中にたまった毛玉を出すために吐くことがよくあります。
特に換毛期は毛を吸い込まないようにマメに掃除しましょう。
ゲージの周りやベッド・毛布にたくさん毛がついている場合があるのでチェックしましょう。
◆ ストレス
犬は環境の変化などのストレスで嘔吐、下痢、便秘などの消化器症状が出ることが多いです。
・ペットホテルに預けられた
・長い時間独りで留守番した
・ゲージの位置が変わった
・家族が病気になった …など
愛犬がストレスに感じていることがないかチェックしてみましょう。
犬が吐いた後の食事や水はどうしたらよい?

犬が嘔吐した後の食事は段階的に増やしていきます。
・半日から1日は水、食事を与えずに様子をみる
![]()
・嘔吐が止まったら少量の水をあげてみて、吐かないようだったら水の量を増やす
![]()
・水を吐かずに落ち着いてきたらふやかしたドッグフードなどの消化しやすい
食事を少量から開始する
![]()
・2から3日ほどは一度にたくさん食事を与えず、少量を小分けにあげる
 食欲が出てきたからといって、いきなりたくさん与えるとぶり返すことがあるので注意しましょう。
食欲が出てきたからといって、いきなりたくさん与えるとぶり返すことがあるので注意しましょう。
続いて犬が嘔吐しやすい場合の食事対策を説明します。
犬が嘔吐しやすい場合の対処法
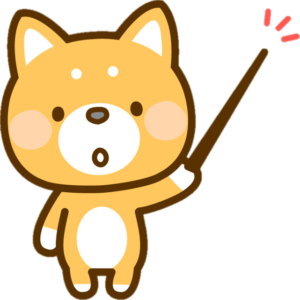
犬の嘔吐には病気だけでなく、普段の習慣の中にも原因が多くあることがわかります。
犬は何度か吐くことを覚えると癖になってしまうことがあります。
食事の与え方、ドッグフードの種類、散歩のタイミングなど改善できることは実践して、嘔吐が癖にならないようにしましょう。
人間と同様にワンちゃんにも体質や性格があります。
緊張しやすい性格、消化が苦手な体質、腸内環境が乱れているといったことで、嘔吐、下痢、便秘などの胃腸の症状が出やすくなります。
ストレスを感じやすい犬の対処法
同じ環境でもストレスに感じる犬とそうでない犬がいます。
こういった違いは生まれつきの性格なのですが、飼い主さんの対応でちょっとずつ改善できることもあります。
実は緊張しやすい性格のワンちゃんの場合、飼い主さん自身も几帳面すぎたり、心配症であることが多いのです。
愛犬のちょっとした反応や変化に「どうしたのかしら?」「大丈夫かな?」と反応しすぎないことが大切です。
犬は飼い主に似ると言いますよね。
犬たちは飼い主のことをよく観察しているので仕草や外見だけでなく、性格まで似てきます。
物事に落ち着いて対処して、なるべくおおらかに過ごせるように心がけましょう。
嘔吐しやすい犬の食事対策
体質的に消化器トラブルが多いワンちゃんの食事は次の3つの点に注意します。
1.消化が良いものを与える
2.少ない量でも栄養価が高いものを与える
3.少ない量でもカロリーが高いものを与える
消化器トラブルのある犬は、胃や腸に生まれつきの問題を抱えていることが多いです。
そのため、犬の胃・腸に負担をかけず、栄養をしっかり補給することが大切なのです。
栄養をしっかり補給するには高カロリー、高たんぱく、高脂肪の食事が必要です。
さらに消化を良くするためには良質なたんぱく質と脂肪が重要です。
食物繊維は消化が悪いので控えめにしてください。
【手作りフードの場合】
茹でたお肉やお魚を細かく刻んでから食べさせます。
レバーを茹でてフードプロセッサーにかけ、レバーペーストにするのもおススメです。
野菜はじっくり火を通して、細かく刻むかフードプロセッサーでつぶして与えます。
ただし野菜は消化が悪いので割合を少なくしてください。
お肉が6~7、野菜が3~4くらいの割合です。
【ドッグフードの場合】
ドッグフードを選ぶ場合は、量が少なくても十分な栄養が摂れるように、良質な動物性たんぱく質(肉・魚)が豊富なものを選びます。
消化の悪い穀物がたくさん入っているドッグフードは避けてください。
しかし一般的に市販されているドッグフードでは嘔吐を減らすことが難しいのも現実です。
かと言って手作りフードは手間がかかりますし、栄養バランスを考えるのが大変です。
そんな時は消化器トラブル専用のドッグフードや、お腹健康を考えて乳酸菌が入っているフードを選ぶのが最適です。
嘔吐物による2次感染を防ぐ

嘔吐物の後片付けがきちんと行われないと、犬がその場所を舐めたりして嘔吐を繰り返す原因になります。
それから犬の嘔吐物に含まれる寄生虫や菌、ウイルスの中には人間や他のペットに感染するものがあります。
嘔吐物の始末や掃除をする時には必ずビニール手袋などを使用してください。
確実に除菌できるスプレーできれいに後始末をして、手洗いも十分に行い2次感染を防ぎましょう。